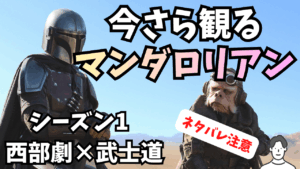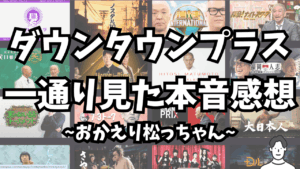This is water「これは水です」2005年ケニオン大学卒業式:作家デイヴィッド・フォスター・ウォレスの名スピーチ全訳
2005年のケニオン大学卒業式で語られたデイヴィッド・フォスター・ウォレスのスピーチ「This is Water(これが水だ)」は、当たり前に流れる日常の中で何を見落としているのかを静かに問いかける名演説です。
本記事はその全文を自然な日本語に訳して紹介します。
あくまで一例として、参考程度にしてください。
*原文に小見出しはなく、こちらで追加したものです。
目次
魚の寓話
保護者の皆様、そしてケニオン大学2005年度卒業生の皆さん、おめでとうございます。
2匹の若い魚が泳いでいると、逆向きに泳いできた年配の魚に出くわしました。
年配の魚は彼らに頷きかけて、「おはよう、君たち。水はいかがかね?」と言いました。
2匹の若い魚はしばらく泳ぎ続けましたが、やがてそのうちの1匹がもう1匹を見て、「一体、水って何だよ?」と言いました。
卒業式の慣習と陳腐さの効用
これはアメリカの卒業式スピーチで定番の手法──教訓的な小さな寓話を用いるというものです。
物語という形式は、このジャンルの中では比較的まともな慣習です。もし私がここで、賢い年老いた魚になって若い魚たちに水の説明をしようとしているのではと心配するなら、どうか安心してください。私は賢い年老いた魚ではありません。魚の話の要点は、最も明白で重要な現実こそ、往々にしていちばん見えにくく、語りにくいということです。
もちろん英語の一文として言えばこれは陳腐な決まり文句に過ぎませんが、実際のところ、日々の大人の生活という戦場では、そうした陳腐な決まり文句が生死にかかわるほど重要になることがあります。少なくとも、この乾いた麗らかな朝に、私があなた方に示唆したいのはそういうことです。
リベラルアーツ教育の「意味」
この種のスピーチの主目的は、あなた方のリベラルアーツ教育がなぜ単なる物質的報酬以上の人間的価値を持つのかを語ることです。
そこで卒業式スピーチの常套句──「リベラルアーツ教育は知識を詰め込むことではなく、考えることを教える」──について話しましょう。
学生時代の私のように、この言い方が嫌いで、誰かに「考え方」を教わる必要があるとは侮辱のように感じる人もいるでしょう。こんな優れた大学に入れたという事実自体が、すでに考える力を持っている証だと感じるのは自然です。
しかし私が言いたいのは、この常套句は侮辱ではなく、むしろ的確だということです。なぜなら本当に重要な思考の教育とは、考える能力そのものではなく、何を考えるかを選ぶ力だからです。
もし「何を考えるか選ぶ自由」が明白すぎると思うなら、魚と水のことを考えてみて、明白なものの価値に対する懐疑をほんの数分間だけ脇に置いてみてください。
別の寓話(アラスカでの議論)
別の物語を紹介します。
アラスカの辺境のバーに二人の男がいて、1人は信心深く、もう1人は無神論者です。
四杯目のビールが入ったあとの特有の激しさで神の存在について議論していました。
無神論者は言います。「神を信じないのには理由がある。祈りを試したことがないわけじゃない。先月、ひどい吹雪で道に迷い、気温はマイナス50度だった。雪の中でひざまずいて『ああ神よ、助けてくれ』と叫んだんだ。」
バーの宗教家は言います。「それなら信じるだろう、だって君は生きているじゃないか。」
無神論者は目を丸くして答えます。「違うよ。ただ通りかかった人たちがたまたま助けてくれて道を教えてくれただけだ。」
経験の解釈と信念の起源
この話は、同じ経験が異なる信念の枠組みからは全く違う意味を持ちうることを示します。リベラルアーツ的分析はここで多様性と寛容を尊ぶので、一方が正しくて他方が間違っているとは単純には言いません。
それは良いことですが、同時に私たちはこうした信念のテンプレートがどこから来るのか、つまりその人の内面のどこから生じるのかをあまり問わないことが多いのです。
あたかも世界への基本的な向き合い方が身長や靴のサイズのように生まれつき決まっているか、言語のように文化から自動的に吸収されるかのように扱われがちです。
しかし実際には、意味の構築は個人的で意図的な選択の問題です。さらに問題なのは傲慢さです。
無神論者は通りかかった人たちの行為と自分の祈りを結びつける可能性をあっさり退けています。宗教的な人々もまた確信に満ちて傲慢に見えることがありますが、教条主義者の問題は不信心者のそれと同根です──盲信的な確信、閉ざされた心、それは囚人が自分が檻にいることさえ気付かないほどの監獄です。
何を学ぶべきか――傲慢さを減らすこと
ここでの核心は、私が「いかに考えるかを教える」というときに本当に意味していることの一部は、少しだけ傲慢さを和らげること、自分と自分の確信に対してわずかな批判的自己認識を持つことだという点です。
私が自動的に当然だと信じていることの多くは、実は誤りで妄想に過ぎないことが多いと、私は苦い経験から学びました。
皆さんもそうなるでしょう。
自己中心性(デフォルト設定)
一例を挙げます。私の即時的な経験はすべて、私が宇宙の中心であるという深い信念を裏付けるように見えます。自分が最もリアルで鮮やかで重要な人物であると感じるのです。
こうした自然な自己中心性は社会的に忌避されるためあまり顧みられませんが、ほとんどの人に共通する「デフォルト設定」です。
経験とは常に「私」の前に、後ろに、左に、右に広がっており、他人の思考や感情は伝達されなければなりませんが、自分の感覚は即時的で切迫して感じられます。
これは美徳の問題ではありません。問題は、この生まれつきの既定の設定から自由になるための仕事を自分で選ぶかどうかです。
既定の設定を調整できる人は「well-adjusted(うまく適応している)」と呼ばれますが、それは偶然の表現ではありません。
知性の罠と注意を保つことの困難さ
学問的環境にいると、物事を過度に知性化してしまう危険があります。目の前で起こっていること、自分の内側で起こっていることに注意する代わりに、頭の中で抽象的議論に迷い込む──これが起こりがちです。
頭の中の絶え間ない独白に催眠をかけられることなく、警戒し、注意を保ち続けるのはとても難しいのです(今まさにそうかもしれません)。
「考えること」の本当の意味――選ぶ力
卒業から20年経って私が理解したのは、「考えることを教える」という常套句は、何を、どのように考えるかをコントロールする力を身につけることの省略形だということです。
意識的で気づきのある状態で、何に注意を払うか、経験からどのように意味を構築するかを選べること。大人になってこの選択ができなければ、まずいことになります。古い言い方を借りれば「心はすばらしい召使いだが、恐ろしい主人である」ということです。
多くの陳腐な格言と同様に、この一句は偉大で恐ろしい真実を表しています。銃で自殺する人間が頭を撃つのは偶然ではありません──彼らは恐ろしい主人を撃っているのです。そして多くの場合、その引き金を引く以前に心は既に死んでいるのです。
リベラルアーツ教育の本当の価値
だから私が言うのは、これこそがリベラルアーツ教育の本当の価値です。
快適で裕福で立派な大人としての人生を、生きながらにして死んでいるような、無意識の奴隷として過ごさないための方法を学ぶことです。
日常の具体例(些細なフラストレーション)
これは誇張や抽象ではなく、具体的です。卒業生の皆さんはまだ「日々」が本当に何を意味するかを知らないでしょう。成人生活には、退屈や日常、些細なフラストレーションが山ほどあります──ここにいる保護者や年長の方々はよくご存知でしょう。
ある普通の日を想像してください。朝起きて白襟の仕事に行き、8〜10時間働き、夜は疲れて早く休みたい。しかし食べるものがないことに気づき、仕事帰りに車を走らせスーパーマーケットへ。終業時間の渋滞、店内の混雑、過度に明るい照明、魂を殺すようなBGM。欲しいものを探して通路を彷徨い、へたくそなカートを操り、ようやく夕食の材料を揃えるも、レジが少なく長い列に並ばされる──といった具合です。
店員の疲弊した態度、列での他人の振る舞いに腹が立ち、最後に「良い一日を」と死んだ声で言われる。その後もガタガタの駐車場を抜け、ラッシュの渋滞の中を運転して家に戻る。こうしたことが、日々のルーチンとなって積み重なっていきます。
些細な場面が選択の場になる
要点はここです。こうした些細でイライラする出来事が、何に注意を向け、どう考えるかを選ぶ訓練の場になるということです。
何も選ばなければ、ただイライラし続けるでしょう。デフォルト設定では、「これは全部自分のせいだ」「他人が邪魔をしているだけだ」と感じがちです。
別の見方を選ぶこと
しかし別の見方も可能です。
渋滞で前のSUVの運転手を責める代わりに、その人がかつてひどい事故に遭い、今は安全に感じるために大型車を選ばざるを得なかったのかもしれないと想像すること。追い越していったハマーは隣に病気の子を乗せた父親で、病院に向かっていたのかもしれない。レジのあの女性は、深刻な病で臥せる配偶者の手を握り続けて徹夜したのかもしれない。あるいは行政の仕事で小さな親切をあなたの家族にしてくれた人かもしれません。
これらは可能性として低いかもしれませんが、不可能ではありません。何を考慮するかはあなた次第です。既定の設定でいる限り、そうした可能性を考慮しないでしょうが、注意の仕方を学べば、違う世界が見えてきます。
注意を向けることで得られるもの
注意を学べば、混雑で暑く遅い消費者地獄のような状況が、意味深く、あるいは神聖にさえ感じられることがあります。愛や友情、物事を結びつける深い一体感の火で燃えることもありうるのです。
もちろん、その神秘的な解釈が必ずしも「真実」であるとは限りません。だが大文字のTの真実は、あなたがそれをどう見ようと決められるという事実です。
教育の自由と「何を崇拝するか」の選択
これが本当の教育の自由であり、well-adjustedであることを学ぶ自由です。あなたは何が意味を持ち、何が持たないかを意識的に決められます。何を崇拝するかを決められるのです。
なぜこれは重要か。日常の戦場では、無神論というものは実際には存在しません。崇拝しないことなどなく、誰もが何かを崇拝しています。与えられた選択は「何を崇拝するか」だけです。イエス・キリストであれアッラーであれ、あるいは倫理原則であれ、何かを崇拝することを選ぶのには理由があります。ほとんどそれ以外のものを崇拝すると、それがあなたを食い尽くすからです。
もしお金や物を崇拝すれば、決して十分とは感じられません。体や美しさを崇拝すれば、やがて老いが訪れ、何度も「死」を味わうでしょう。こうした真実は昔から神話やことわざ、寓話として語り継がれてきました。秘訣は、この真実を日々の意識の最前線に保つことです。
力を崇拝すれば、弱さと恐怖が増し、さらに他者を支配して恐れを麻痺させたくなります。知性を崇拝すれば、常に自分が詐欺師であるように感じるでしょう。しかしこれらの崇拝が陰湿なのは、それ自体が邪悪なのではなく、無意識である点です。気づかぬうちに既定の設定へ滑り込み、何を見てどのように価値を測るかを無自覚に選んでしまうのです。
現実世界と文化の力
現実世界は既定の設定で行動することを後押しします。人と金と権力の世界は恐れ、怒り、渇望、自己崇拝のプールの上で機能しており、私たちの文化はそれらを利用して巨大な富と快適さ、個人の自由を生み出しました。この自由には確かに良い面があります──自分の小さな頭蓋骨サイズの王国で領主として振る舞う自由です。だが真に価値ある自由は別にあります。
それは注意力と気づき、規律を伴う自由であり、他者を本当に気遣い、日々の地味で目立たない犠牲を繰り返す能力です。これが本当の自由であり、教育された状態であることの意味であり、「いかに考えるか」を理解するということです。対して代替は無意識であり、既定の設定、ラットレース、そして何か無限のものを持っているという錯覚と喪失感です。
結論――大文字のTの真実(死の前の生)
この話は卒業式らしい軽やかな祭りの演説の形式にはそぐわないかもしれません。私にとってこれは修辞を取り去った大文字のTの真実です。どう思うかは自由ですが、単なる説教として切り捨てないでください。この話は道徳や宗教、教義、死後の世界といったことだけを語るものではありません。
大文字のTの真実は「死の前の生」についてのものです。
本当の教育の価値は知識そのものにあるのではなく、単純な気づきにあります。何が本当にリアルで本質的なのか、私たちの周りのありふれた景色の中に常に隠れているその何かに、繰り返し自分を向け続けることです。
最後に繰り返します──
「これが水だ。」 「これが水だ。」
大人の世界で日々、意識的に、生きたままでいることは想像を絶するほど困難です。だからまた別の陳腐な常套句が真実になります。あなた方の教育は本当に一生の仕事です。そして今、それが始まる。
幸運を遥かに超えるものを、あなた方に願っています。
最後に:要約とまとめ
全文読むのも大変だと思うので、最後に特に大切だと思うメッセージを5つにまとめておきます。
1. 最も重要で、ありふれた現実に気づくこと
スピーチは「水」の寓話で始まります。
魚にとって不可欠な「水」のように、私たちにとって最も重要で、生きる上で欠かせない現実(環境、価値観、信念など)は、あまりにも身近すぎて見えにくく、語られにくい。
真の教育とは、この「水」が何であるかを認識し続けることです。
2. 人間の「デフォルト設定」からの解放
人間は本能的に「自分が宇宙の中心である」という自己中心的な「既定の設定(デフォルト設定)」を持って生まれています。これは退屈で、苛立たしく、無意味に思える日常のルーティン(渋滞や混雑したスーパーなど)において、他者を排除し、自分だけの不満に囚われる原因となります。
宗教家と無神論者の話のように、私たちは自分の信念や解釈が「絶対的に正しい」と盲目的に確信しがちです。真の教育とは、傲慢さを捨て、自分自身の確信や思考に批判的な意識を持つことから始まります。
3. リベラルアーツ教育の真の価値
リベラルアーツ教育の真の価値は、知識を詰め込むことではなく、「いかに考えるか」を学ぶこと、つまり「何を考えるかを選択する」能力を身につけることです。
「心は優れた召使いだが、恐ろしい主人である」というように、自分の頭(思考の自動的な流れ)の奴隷になるのではなく、意識的に、何を考え、何に注意を払うかをコントロールする努力をすること。
これが大人の生活を「死んだ」「無意識な」状態で過ごさないための唯一の方法です。
4. 人は何かを必ず“崇拝”してしまう。
皆、必ず何かを崇拝しています。
お金、美しさ、力、知性など、自分自身以外のものを崇拝するなら、それは決して満たされず、最終的に自分を食い尽くし、不幸にする。
最も貴重な自由とは、注意と意識と規律をもって、日々、誰にも見えない「地味で地道な方法」で他者を気遣い、彼らのために犠牲を払うことができることです。
これこそが、人生を意味深く、神聖なものとして経験する力であり、本当の教育がもたらすものです。
5. 大文字のTの真実
ウォレス氏が卒業生に伝えたかった「大文字のTの真実」は、「死後の生」ではなく「死の前の生」に関するものです。
それは、知識ではなく「単純な意識(Simple Awareness)」に関わる、一生をかけた仕事です。
日々のルーティンの中で、自分が自己中心的なデフォルト設定に陥っていることに気づき、意識的な選択と他者への配慮をもって生きることで、「水」の中で溺れずに生きた状態を保つこと。
自分中心の視界から抜け出し、他者の可能性や物語を想像し、日常のイライラやつまらなさを別の角度から捉え直す努力。
それが、死ぬ前に“生きた”と言える人生を作る。